人気記事一覧
「休眠預金って?」と思った方にお勧めのリンク先をまとめました。ご活用ください。
-業務改善PTの経過報告- よりよい休眠預金活用事業を一緒に考え作り上げていくために!
資金分配団体と指定活用団体であるJANPIAが、よりよい休眠預金活用事業を作り上げていくために、共に取り組む「業務改善PT(プロジェクトチーム)」。今回はJANPIA事務局から、業務改善PT立ち上げの経緯や現在の活動の経過についての話を伺いました。(休眠預金活用事業サイト編集部)
2019年度通常枠で採択された資金分配団体のリストです。
JANPIAのウェブサイトにおいて、2024年度通常枠〈第2回〉資金分配団体として、14事業(14団体)が発表されましたので、ご紹介します。
資金分配団体による「実行団体の公募」の情報をお届けします。掲載情報は2022年5月26日時点でJANPIA広報担当で把握している内容です。最新の情報については、資金分配団体ウェブサイトをご確認いただくか、直接資金分配団体にお問い合わせください。
JANPIAのウェブサイトにおいて、2021年度通常枠〈第1回〉資金分配団体として11団体11事業が発表されました。
人権を守るために福祉を充実させる。富田林市人権協議会が取り組む「I♡新小校区福祉プロジェクト」
大阪府富田林市を拠点に、差別のない人権尊重のまちづくりの実現に向けて活動する「一般社団法人富田林市人権協議会」。 時代の移り変わりから、地域コミュニティの低下が懸念されている昨今。2019年度の休眠預金活用事業(通常枠)では、「オープンなつながりでコミュニティをつなぎ直す」をテーマに、集いの場・居場所づくりや地域有償ボランティアシステムづくりなどに取り組みました。2022年度に採択された事業では、子ども食堂や居場所づくりをサポートしています。 今回は、同団体事務局長の長橋淳美さんにこれらの取り組みについてお話を伺いました。
「ダブルハルカヌー」で目指す体験格差ゼロ社会!|-SHIPMAN-
「ダブルハルカヌーって安全性が高いんですよ」。そう爽やかな笑顔で話してくださったのは、有限会社SHIPMANの代表取締役を務める城田守さん。2019年度通常枠〈資金分配団体:公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団〉の実行団体として、活動拠点である静岡県立三ヶ日青年の家(以下、青年の家)を舞台に浜名湖畔で体験格差をなくすべく、水辺の活動やさまざまな支援に取り組んでいます。今回は、日本でここにしかない「ダブルハルカヌー」に特別支援学校の子どもたちが挑戦!その体験学習の様子、そして休眠預金を活用したSHIPMANの取り組みなどを取材しました。
地域と家族がシームレスに寄り添う空間を。「手賀沼まんだら」が目指す、これからの子育ての形
千葉県北部の柏市、我孫子市、白井市、印西市などにまたがる湖沼・手賀沼。ここをフィールドに、地域の人々がつながり、縁をつくるコミュニティを運営しているのが「手賀沼まんだら」です。2019年の設立以来、イベントや場づくりに取り組んでおり、2020年と2022年度の休眠預金活用事業(コロナ枠)を活用したことで、コミュニティプレイスの創出や共食プロジェクトなど、さらに活動の場を広げてきました。今回は、「子ども」と「地域」をキーワードにはじまったという団体の取り組みや、設立から5年が経過してこそ思う活動のおもしろさ、今後の展望などについて、代表の澤田直子さんにお話を伺います。
地道なコミュニケーションが継続的支援につながる。 長野県諏訪圏域にみる「こども食堂支援」
資金分配団体である『認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ』は、新型コロナウイルス対応緊急支援助成で実施する「子どもの居場所作り応援事業」をともにする5つの実行団体を巡り、日頃の活動状況や課題点などについて話す場を設けました。 今回は、実行団体の1つである長野県の『諏訪圏域子ども応援プラットフォーム』の皆さんとオンラインで実施した「これまでの活動の振り返りや、途中経過の報告会」の様子をレポートします。(休眠預金活用事業サイト編集部)
「休眠預金活用事業サイト」には資金分配団体・実行団体が実施しているたくさんの助成事業の情報が掲載されています。 この記事では、『「事業情報」の検索方法』をご案内します。
誰もが支え合える社会を目指して。NPO法人Linoの沖縄海洋リハビリツアー!
人生で初めて海に入った日のことを、覚えていますか? 飛行機に乗ること、旅行に行くこと、自由に海で泳ぐこと。そんな体験をかけがえのない思い出として、医療的ケア児とその家族に届けている団体があります。2019年度通常枠の実行団体である「NPO法人Lino」です(資金分配団体:公益財団法人 お金をまわそう基金)。今回はLinoが立ち上げ当初から続けてきた、沖縄海洋リハビリツアーに密着。医療的ケア児とその家族が体験した初めての海、その先にLinoが目指す社会のあり方について、Lino代表の杉本ゆかりさんのお話とともにお届けします。
資金分配団体に聞く社会的インパクト評価への挑戦Ⅱ|ちくご川コミュニティ財団
一般財団法人ちくご川コミュニティ財団(福岡県久留米市)は、2020年度から福岡県久留米市を中心とした筑後川流域の実行団体の伴走を続けています。ちくご川コミュニティ財団 理事でありプログラムオフィサーでもある庄田清人さんは、理学療法士の経験から「評価は治療と表裏一体だった」と話し、治療と同じように事業にとっても評価が重要だと指摘します。社会的インパクト評価に対する考え方や、実行団体に「社会的インパクト評価」を浸透させるためのアプローチについて聞きました。(「資金分配団体に聞く社会的インパクト評価への挑戦Ⅱ」です)
困っている人のSOSを見つけて解決しよう ワークショップで学ぶ「休眠預金活用」
2021年3月13日(土)、東京都江戸川区立船堀小学校の6年生を対象に「出前授業」を実施しました。出前授業とは、社会人講師が小中学校へ出向き、それぞれが得意とする分野などについて特別授業を行うこと。今回は私たちJANPIAがワークショップを織り交ぜながら、「休眠預金活用」についての授業を行いました。
2020年度通常枠で採択された資金分配団体のリストです。
JANPIAのウェブサイトにおいて、2023年度通常枠〈第2回〉資金分配団体として、4事業(4団体)が発表されましたので、紹介します。
JANPIA主催「休眠預金活用事業シンポジウム2024」のご案内
休眠預金活用事業に係るイベント・セミナー等をご案内するページです。今回は、JANPIAが主催する「休眠預金活用事業シンポジウム2024-学びと価値の共有 総合評価から見えてきたこと-」を紹介します。
防災の鍵は「ネットワーク」の形成。支援を現場につなぐ上で必要なことは?|全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)
台風、地震、豪雨、洪水、土砂災害……日本はその立地や地形、気象などの条件から、災害が発生しやすい国土と言われています。いつどこで起きるかわからない災害に備えて活動されているのが、資金分配団体(2019年度通常枠)である「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)」と、その3つの実行団体である「北の国災害サポートチーム」「いわて連携復興センター」「岡山NPOセンター」です。4団体が目標として掲げている共通のキーワードが「ネットワークの構築」。4団体への取材から、災害時に地域内外の団体が連携するためには、平時から組織を超えたつながりが大事だということが見えてきました。
ベトナム人の命と人権を守るために。「日越ともいき支援会」が行う、幅広い支援のかたち
東京都を拠点に、ベトナム人技能実習生や留学生への支援活動を行う「日越ともいき支援会」。日本に在留するベトナム人の技能実習生や留学生の数は急増していますが、劣悪な環境に置かれていることも少なくありません。「日越ともいき支援会」は、そんなベトナム人の「駆け込み寺」として、住居の確保、帰国できない若者の保護、就労支援など、さまざまな活動を行っています。2020年度、2021年度の休眠預金活用事業(コロナ枠)では、コロナ禍で生活困窮者となった約1万人以上のベトナム人を支援してきました。今回は、コロナ禍、そして現在の支援事業について、同団体の代表理事・吉水慈豊さんにお話を伺いました。
年間で136tの食料を集め、延べ4,000世帯を支援。フードバンク北九州ライフアゲインが証明する、“共助”の強さ
2013年に福岡県初のフードバンク団体として設立された、NPO法人フードバンク北九州ライフアゲインは、「すべての子どもたちが大切とされる社会」を目指し、子育て世帯を中心とした食料支援に取り組んでいます。コロナ禍で急増した「食料支援の需要」と「食品ロス」の問題を受けて、同団体は食料を配布するだけでなく、サプライチェーンの効率化やステークホルダーの連携促進にも尽力しています。食料品店、中間支援組織、行政等と協力して22年度に集まった食料品は136t以上。月35世帯ほどだった支援規模は月100〜150世帯にまで増加しました。こうした功績の背景にはどんな工夫があったのか。理事の陶山惠子さんにお話を伺いました。
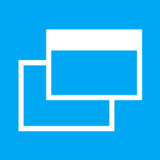


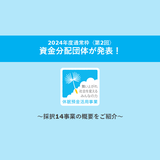




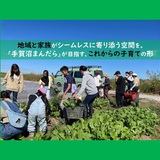






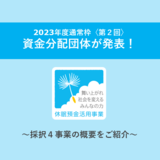




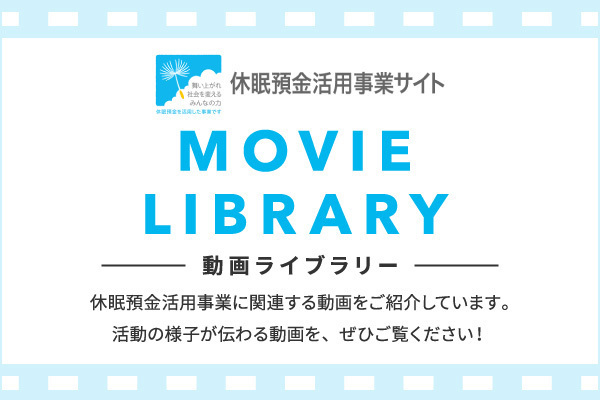



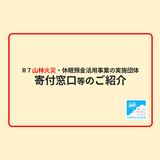
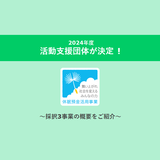
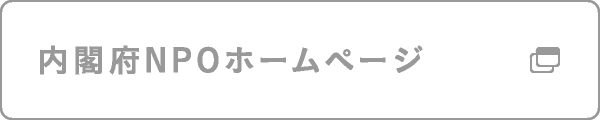
![民間公益活用促進のための休眠預金等活用[内閣府]バナー](https://kyuminyokin.info/uploads/image_manager/image/7/ee293b9f-30b3-427d-8763-29fcdc340984.png)
